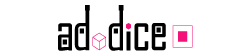AIで何が解決できるのか?

テレビでAI(人工知能 Artificial Intelligence)が紹介されることが増えてきましたが、AIの活用でも消費者がわかりやすいもの、例えば、コールセンターや応対ロボットなどで使われるようになってきた対話AIや自動運転装置、囲碁を打つAIなどが中心です。一方で、企業の中や企業間で使われるAIの活用はほとんど報道されていません。
そのため、AIで何か自動でできる気はするけど、具体的な活用シーンのイメージがつかない人も多いのではないでしょうか。また、消費者向けならAIが色々できるようになったみたいだが、企業活動で本格的に活用できるのはまだ先だろうと考えている人もいらっしゃったり、もったいないなと感じることがよくあります。
そこで、今回は、最近騒がれるようになった深層学習(Deep Learning)を活用したAIで、何ができるようになったのか、まずは目視検査に絞って解説していきます。
従来のAIで解決できないこと
AIとは、簡単に言うと、人が作った人間に近い思考ができる機械です。その思考を導き出すためにどう機械に学習させるのかという手法の研究が学者や企業により進められており、様々な手法を採用したAIが誕生しています。
AIと一言に言っても、何をさせたいかによって採用する手法も異なります。単に機械的に〇か×かを判断させたいだけなのか、鉄腕アトムのように自ら思考し行動する脳みそを作りたいのか・・
ここ数年のAIブームで実生活におけるAIの活用が幅広く拡がり、少し昔に開発されていた手法も活用が進んでいます。
エキスパート型AIの問題点(ルールベースの仕組みの問題点)
1980年代の第2次AIブームの時点で、エキスパート型と呼ばれるAIは既に実用化されていました。膨大な症例を参照し診断支援を行う仕組みなどは、このエキスパート型AIを利用したものです。
ルールベースと呼ばれることもあるエキスパート型のAIは、専門家の複雑で膨大な判断過程を、大人数のデータサイエンティストを客先に派遣するSI(システムインテグレーション)のビジネスモデルと相性が良いため、大手IT企業は力を入れて営業しています。
一方で、ルールベースの仕組みでは適切に解決出来ない課題もあります。たしかに、寸法を計測するタスクや一定の値を超えたか否かで制御を変えるタスクのようにルールベースの仕組みに合う課題もあります。
しかし、毎回一定ではなく少しずつ揺らぎがありグレーな判断が要求される異物やキズあるいは凹みなどをルールベースで検出しようとすると、新たな異物が出る度に検出条件を追加するというイタチごっこになってしまいます。
機械学習型AIの問題点
また、2000年代から台頭してきている機械学習にも限界があります。
一つ目に、精度の問題です。
ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)という画像認識の技術革新を目的にした国際的なコンテストがあります。2011年までは機械学習のニューラルネットワーク以外の手法が主流でしたが、精度は70%台が限界でした。2012年以降は機械学習の一手法に過ぎなかったニューラルネットワークを多層化した深層学習(Deep Learning)が主流になり97%を超える精度を叩き出しています。
歴史的な役目を終えたとして、コンテストの運営主体もスタンフォード大学からカグルというIT人材ビジネスの会社に運営を移管してしまった程です。
二つ目は事実上の限界です。
課題に応じて機械学習の手法を切替ながら試行錯誤をする必要があるので、経験豊富で知見が多く柔軟に試行錯誤ができるデータサイエンティストを確保する必要があります。
しかし、そのようなデータサイエンティストは世界的にも数がいません。この20年ほどAIは冬の時代が続いていて人材育成の仕組みが途絶えそうになっていたところに、急にAIバブルが発生したので使える人材は引く手あまたで人材市場に良い人が滅多に出てこないからです。
かつ、深層学習(Deep Learning)は元々は機械学習の一つの手法に過ぎなかったので、昔から機械学習に携わっている人が必ずしも深層学習を熟知しているわけではなく、むしろ少し前まではニューラルネットワーク限界論が主流だったので「経験豊富」だからこそ深層学習について斜に構えている人も多いという問題もあります。
医療の現場での課題
このような限界を克服できる切り札として期待されているのが、HORUS AI(ホルスAI)のように深層学習(Deep Learning)を用いた最先端のAIです。言葉で表現しきれない勘と経験の世界をデータサイエンティストなしで、システムに取り込むことができるので、その応用範囲の広さから大きな期待が寄せられています。
例えば、医療の世界では従来のシステムでは病理医の判断をシステム化ができないため非常に大きな負担がかかっていました。
がん診断の例で説明しましょう。がん疑いがある時は、精密検査が行われ様々な診断手法を使い診断を下しますが、その中で疑いのある箇所から細胞・組織を切って摘出し、プレパラートにしてから顕微鏡で診断する組織診・細胞診という手法があります。
光学顕微鏡で覗くことも出来ますが、デジタルスキャナでプレパラートをスキャンしてデジタルデータにすればPCのモニターで確認できます。細胞が幾つか連なって形成された組織が癌化する場合もありますが、一つ一つの細胞が癌になってしまう場合もあります。
細胞は20μm(ミクロン)程度と小さいので高解像度で撮影してデジタル化する必要があり、数cmのプレパラートでもPCモニターで81面ほど表示されます。1面を舐めるように精査し、それを81面にわたって走査していく作業は非常に骨が折れる作業です。1面30秒としても40分はかかります。
見逃せば人命にかかわるので大きなストレスがかかります。見逃し事故が起きる背景には、このように本来的に難しい作業が横たわっているからです。
工場の現場での課題
工業の世界でも、医療の世界と同様に、勘と経験が必要な業務(官能検査とマテリアル・ハンドリング)は、システム化ができないので人間の検査員が従事しています。
今回のテーマである目視検査も、システム化が進んでいません。世界的に見て工場労働は3K労働として嫌われる傾向がある中で、人員不足により「仕事はあるのに受注できない」という問題が顕在化し始めており、目視による異物検査や不良分類の自動化が求められているのです。
グレーな判断が必要な領域は、やっていることの内容を言葉で明示的に説明しきれません。言葉で表現しきれないものはルールベースの仕組みに乗らないので、従来のAIでは対応が出来ません。人が限度見本と呼ばれる不良のサンプルを参考に判断します。
また、検査マニュアルに載っている画像を参考にして検知・分類を行います。しかし、同じガイドラインを参照していても、人によって判断に差が生じます。医療でセカンドオピニオンを勧めるのも同じ理由です。
現状、会社同士の取引で、生産側の出荷前検査と製品受入側の検査(受入検品)は別々の人が行っていて、受入側が納得いかない場合は、生産側は返品買取をしなくてはなりません。取決め内容によっては、受入側は受入直後には検査を行わず、加工の最中に気付いた不良を返品する場合もあります。
クレーム買取代金分の損失だけでなく、出荷検品を行った人にも大きな精神的ストレスがかかる辛い状況があります。
また、システム化を断念し人が行ってきた検査は、処理速度に限界があるため、全数検査ではなく、一部を抜粋して検査するサンプリング検査を行っている場合があります。朝にサンプリングして結果が夕方に出る場合、夕方に不良だと分かった時はその間に生産したものを廃棄することになりロスが生じてしまいます。
また、全数検査を避けられない場合は、検査工程がシステム全体のボトルネックとして全体を律速してしまいます。
深層学習(Deep Learning)型AIの特徴
第2次AIブームの時からある「ルールベース」の仕組みは形式知しかシステム化できません。グレーで曖昧な判断を無理にシステム化しようとすると、定義したパターンから少しでもずれると判定に失敗するので、対応のためにまた定義に条件を作り足すといういたちごっこになりシステムが複雑になります。
ルールベースの仕組みが本質的に適しないグレーな判定が必要な課題に適用すると、基準を厳しくすれば過剰検出してしまい不良の割合が大きくなり過ぎます。そのままでは採算が悪くなるので、不良として検知してしまったものを人間が再判定して問題が無いものを良品扱いする良品戻しが必要になります。また、検知したものを分類することはできません。
第3次AIブームで台頭してきた「機械学習」ですが、前提条件と事前データ調整を行った特殊条件でない限り精度が70%台に止まってしまうため、目視検査に使うという観点では精度が不十分でした。(通販システムの合理化など90%台の精度が無くても、過半を超えてくれるなら実用に足りる場合もあります。)
整理すると、深層学習を使わない手法では、勘と経験が必要となるグレーなものをグレーなままに判断ができず、分類の精度も特殊条件を外すと70%台に低迷してしまうという課題がありました。
ところが、深層学習を使うと、95パーセントを上回る精度を出すことができます。データが十分に集まれば99パーセント以上の精度が出せるので人間の精度を超えます。勘と経験をシステムに取り込みグレーな判断ができるようになるのが深層学習の特徴なのです。
HORUS AIで解決出来ること
このように目視による人の判断を必要としてきた作業工程は、深層学習(Deep Learning)によりシステムに置き換えることができます。
しかし、深層学習をゼロからシステム化するには、最近のトレンドを熟知すると同時に現場の事情をわきまえたデータサイエンティストが必要です。しかし、そういった人材はほぼいません。
また、深層学習ではAIに学習させるために教師データと呼ばれる素のデータをどう解釈するかというデータを作る必要があります。がん診断支援でいうと、画像のどの領域にどのような種類の癌腫があるかというデータです。この教師データ作成は識別眼の持ち主である、長年の経験と勘によりデータの意味を読み解ける人が行う必要があります。
深層学習のためには、データサイエンティスト兼ベテラン現場作業員である必要があるのです。
残念ながらそのようなスーパーマンは、ほどんどおらず、いても自社にとどめておくことは困難です。
アドダイスは、「Enhance human with SoLoMoN」(人の能力を SoLoMoNで増強する)をモットーに、データサイエンティストがいなくてもPCのブラウザを操作できれば、現場作業員の人自身で教師データを作り深層学習を使ったAIの自立運用が可能な仕組みを提供しています。
また、深層学習を実用する場合は、モデルと呼ばれるコンピュータ神経網を何パターンも用意して学習を試し、成績が一番良いものを利用します。しかし、AIの中身まで理解して使いこなすのは知的好奇心を満たしても現場効率には直結しません。
現場監督的には、精度が良ければそれで良いという即物的なニーズに応える必要があります。そこで、AIの中身が分からなくても精度の良い組合せを結果の数字だけで判断できる仕組みを提供しています。
HORUS AIにより、データサイエンティストがいなくても現場作業員だけで深層学習の自立運用が可能になり、目視による人の判断を必要としてきた作業工程を精度を高めて自動化することができるのです。