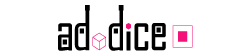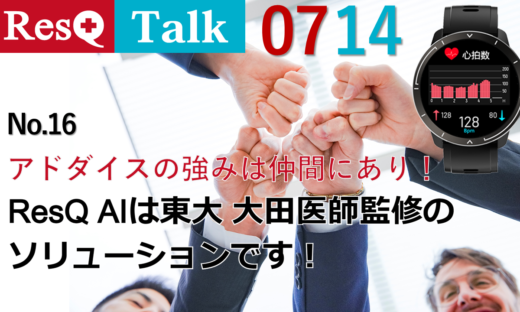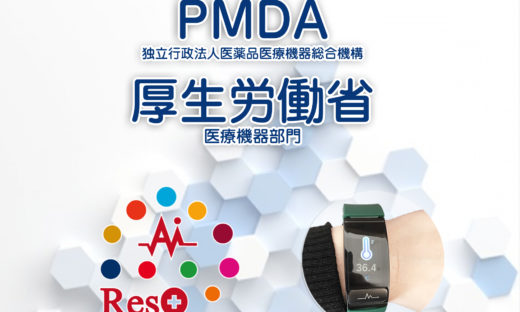「AIと人間の共存」について、茨城県立土浦第一高等学校附属中学の生徒さん達から、夏休みの課外学習の一環で取材を受けました!

8/12(火)、土浦第一高等学校附属中学の4名の生徒さんからオンラインで取材を受けました。同校は、創立127年になる茨城県下の伝統校「土浦第一高等学校」併設型の附属中学として2021年に新設された学校で、今回取材をしてくださったのは4名の生徒さんです。
生徒さんたちは、夏休みの課外学習の一環として「AIと人間の共存」をテーマに研究を行っているとのこと。弊社のヘルスケアAIについて興味を持ち、お問い合わせフォームからご連絡をくださったご縁で、取材の場を設けさせていただきました。
最初の関心は「遠隔地の高齢者の見守り」
まず生徒さん達が興味を持ったのは、過疎地など遠隔地に暮らす高齢者の健康見守りでした。
「ご高齢の方は、スマートウォッチやスマートフォンを使いこなせるのだろうか?」という素朴な心配も出され、そこから会話は、ヘルスケアAIは過疎地での導入を意識しているのかという質問へも展開しました。
私たちからは、都市一極集中は東京だけでなく世界的な傾向であり、過疎地の健康・医療サービス提供が難しくなっている現状を、山梨県やボリビアでの取り組みを例に説明しました。そしてその課題を解決するために、小さな異変を早期に察知し、必要な支援へとつなげることができるヘルスケアAIがあるとお伝えしました。
「課題はどうやって見つけるのか?」
過疎地の健康・医療サービスが例に出ましたが、「お客様の課題や問題は、どうやって見つけていくのか」という質問もいただきました。
これに対しては、逆にこちらから生徒さん達へ「ご自分のスマートフォンで毎日必ず開くアプリは何かありますか?」という質問をさせていただきました。生徒さんからは「LINEやYouTubeです」というお答えでした。ではなぜLINEやYouTubeを毎日必ず、しかも日に何度も見るのでしょうか?
毎日開いてもらえる、継続して使ってもらえるサービスには、必ず「使いたくなる理由」があります。その理由や動機を深く理解することが、顧客課題発見の出発点であり、そこからソリューションを企画・開発していきます、とお話しました。
「未病」の段階でAIがとらえ、知らせてくれるしくみ
ヘルスケアAIのお話の中で、私たちが特に大切にしているのは、「病気になってから」ではなく「病気になる前」のこころと身体の健康ですとお伝えしました。それは日々の生活を整え、病気になる前に病気の芽を摘むという予防のアプローチ、未病の考え方です。
バイタルデータからAIが解析し、こころと身体の不調を早期に察知し知らせることで、結果的に医療や介護の負担を減らし、生活の質を守ることができ、健康寿命の延伸にもつながります。
生徒さんからは、「病気になる前から、生活を整えることで病気を減らすという考え方は大変印象的で、今後の学びに活かしていきたいと思っております」との感想をいただきました。

未来を担う生徒さん達に期待します!
中学生の生徒さんとのお話ということで、取材前、私たちはどんな質問が寄せられるのか、色々と想像していました。
「AI=生成AI」という認識が一般的な昨今ですので(アドダイスのAIは、もちろん生成AIではありません)、「生成AIのようなことができますか?」という質問も飛び出すかな?とも思っていました。AIの仕組みについても聞かれるかな?とも想像していました。
しかしAIの技術的な面ではなく、むしろ社会課題をAIがどう解決するのか、AIが人をどう幸せにするのかなどに着目した的確な質問が多く、事前に入念な下調べと洞察を重ねてこられたのだなと感じる場面が多くありました。
生徒さんたちは、利用者目線の障壁や地域格差といった本質的課題を見抜いており、AIと人間の共存について真剣に考えてくれていたことに、大変感銘を受けました。
生徒さんたちの中から、未来の健康・医療、あるいはAI分野をリードする人材が現れることを、心から願っています。皆さんとお話することで、こちらも希望をいただいた気持ちになりました。ありがとうございました。残り少なくはなりましたが、ぜひ良い夏休みをお過ごしください!